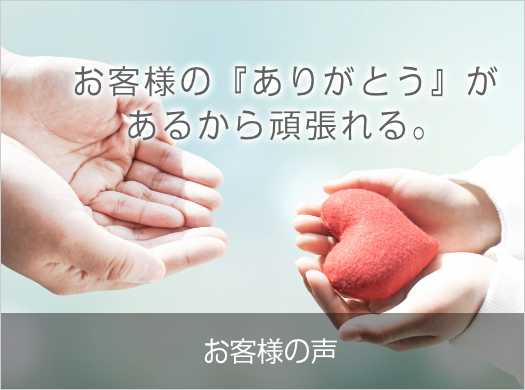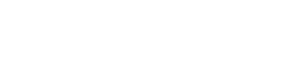続・河豚とは?〜その② フグの形態について
2013年10月22日
 数年前に「ふぐとは?」という題名で、その定義や生態などを記事として投稿しましたが、
数年前に「ふぐとは?」という題名で、その定義や生態などを記事として投稿しましたが、
改めて、意外と知らない河豚のことを紹介してみたいと思います。
今回は、その形態について。
フグの形態について
フグは沿岸性の魚類ですが、前回中国の例でお伝えした通り、河口まで上るものもあります。
続・河豚とは?〜その① フグの名称について
2013年10月18日
 数年前に「ふぐとは?」という題名で、その定義や生態などを記事として投稿しましたが、
数年前に「ふぐとは?」という題名で、その定義や生態などを記事として投稿しましたが、
改めて、意外と知らない河豚のことを紹介してみたいと思います。
今回は、その名称の秘密から。
河豚の名称について
フグ目フグ科に属する海産魚の総称を「河豚(ふぐ)」といいます。
生息地は世界中の温帯、熱帯の海に広く分布し、日本近海には約40種類がいると言われています。
食用として使われるのは、
冬鍋の王様とら河豚をはじめ、
マフグ・クサフグ・サバフグ・ヒガンフグ・コモンフグ・アカメふぐ・ショウサイフグなどがあります。 (more…)
ふぐが最も旨い季節
2012年12月08日

ふぐは昔から、
「秋の彼岸から春の彼岸まで」
「ふぐは橙の色づく頃より食い始め、菜種の花の咲く頃に食い終わる」
といわれて来ました。
いずれも、ふぐと旬の結びつきを現した、なんとなく風情のあることばですよね。
ふぐは活魚で価値が倍増する!?
2012年11月28日

「活魚」は、よく聞く言葉ですね。
今回は、この活魚について掘り下げて書いてみます。
活魚とは、生きたまま調理される魚のことをいいます。
冷凍や日置した魚と違って、活魚は新鮮さがダントツですから、飲食店が店のオリジナル色・差別化する手段として大きなアドバンテージとなりますが、実はこの活魚、結構奥が深いようです。
活魚には、「活魚水槽」という専用の水槽を使うわけですが、この水槽、ただ魚を泳がせておく容器というわけではないのです。
そんな認識で、活魚を行おうとすると、最悪の場合、魚を全滅させてしまう可能でも否定出来ないのです。
ふぐの毒について③
2012年11月20日

前回はふぐの毒の正体、テトロドトキシンについて書きましたが、
現代では既にふぐ毒の解毒法はすでに確立されているというのをご存じですか?
解毒法確率の始めは、昭和三十四年に、当時下関市の水産大学に在籍していた藤井実教授が、亜硫酸ソーダをリン酸で中和処理した混合液(SP剤)で実験したところ、無毒化に成功したのがきっかけだそうです。
ただ、SP剤は直接人体に注射すると有害なため、更に試行錯誤を続けます。 (more…)
冬鍋の王様、とらフグ鍋!
2012年11月12日
 季節毎に食べ物は、一番美味しい時期というものがあります。これを日本では「旬のもの」といいますよね。
季節毎に食べ物は、一番美味しい時期というものがあります。これを日本では「旬のもの」といいますよね。
旬のものは、他の時期にくらべて沢山採れるというだけでなく、栄養的にも味としてもたいへん優れているわけです。
昔から人は、自然と共に暮らし、季節毎に旬のものを大量に食して来たわけですが、資源が枯渇することもなくうまくバランスが取れて来たのです。つまり、旬にそれを食べるということは、人間を含めた自然のひとつの生態系として成り立ってきたとも言えるのかもしれません。
ふぐ食の歴史
2012年11月06日

日本人のフグ食の歴史をさかのぼっていくと、
なんと縄文時代の遺跡からも河豚を食べていた痕跡が見て取れるそうです。
それぐらい日本人は、河豚を昔からよく好んで食べていたのですね。
当然、ふぐの料理方法が確立していなかった昔には、
多くのふぐ中毒も発生していたと推測される訳で、