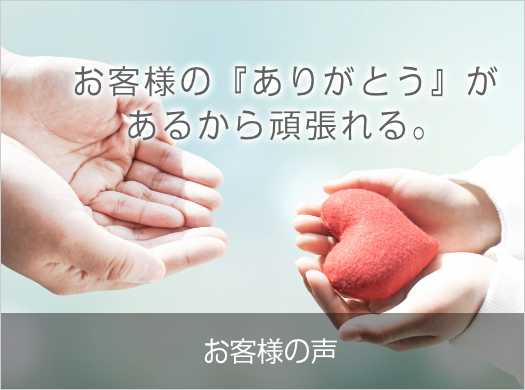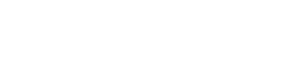ふぐの板前修業③
2012年10月28日

さて、前回は板前として一人前と認められるための10年〜15年という修行期間を説明しました。
これでようやく、「真」になれる条件が整い、
フグの身を引くような難易度の高い仕事が任せて貰えるようになるという訳です。
ふぐの板前修業②
2012年10月24日
前回の「ふぐの板前修業①」の続きです。

「わき坂」の1〜2年を経た後は、
「煮方」の手伝いをする「わきなべ」を更に1〜2年、
そして「盛り付け」を2年、
そしてようやく「向坂」を3年程度勤めて、
一人前扱いとされる「煮方」へと昇格(という表現で良いかは不明..)していくのです。
店の評価を決める「ポン酢」のチカラ
2012年10月17日
 ふぐの肉は淡泊で、肉自体に味を感じづらいとよく言われます。
ふぐの肉は淡泊で、肉自体に味を感じづらいとよく言われます。
そのためか、ふぐの味はポン酢で左右される!と断言される人も結構いらっしゃるようです。
みなさんよくご存じの通り、ポン酢は、ふぐ刺身でその味を引き出すだけではなく、ふぐ鍋からふぐ雑炊まで、本当にふぐ料理のあらゆる場面で使われ、重要な役割を持っています。
つまり、必然的に「ポン酢をどう調合するか」という事が、ふぐ料理店の味の評価に多大な影響を及ぼす、という事になるわけですね。
ふぐの毒について②
2012年10月13日
 ふぐの毒の正体は、「テトロドトキシン」という成分です。
ふぐの毒の正体は、「テトロドトキシン」という成分です。
この早口言葉のような成分の名前は、「四つの歯を持つ」という意味のふぐの学名から名付けられたそうです。
ふぐ毒の科学的な解明への試みは明治四十年代頃から始まったと言われていますが、そういった研究の成果として、「テトロドトキシン」はその神経への強い作用が注目され、鎮痛剤、鎮静剤として医療の現場でも使われているそうです。
ふぐの板前修業①
2012年10月08日
 みなさんは、河豚を調理する板前職人が一人前になるまでの工程をご存じでしょうか?
みなさんは、河豚を調理する板前職人が一人前になるまでの工程をご存じでしょうか?
絵皿の模様を薄造りで透かしながら、「菊」「鶴」「孔雀」等をかたどって、盛りつけられた河豚の刺身こそ、修行を積んだ板前さんの技の見せ所であり、ふぐ料理の醍醐味でもありますよね。
料亭の板場を取り仕切る人のことを、「真」と呼ぶそうです。
「真」は板前を目指す者にとってあこがれであり、そこに至る道はとても厳しいものなのです。
ふぐが美味しいわけ②
2012年10月05日
 料理として使われるふぐは、
料理として使われるふぐは、
「トラフグ」
「マフグ」
「カラスフグ」
「シマフグ」
「サバフグ」
などがあります。 (more…)
下関ふぐのルーツは幕末の志士?
2012年09月30日
下関ふぐのルーツは幕末の志士と言われているのをご存じですか?
日本でふぐを食べるようになったのは江戸時代で、毒のある河豚の調理法が確立して「ふぐ汁」として一般に食べられるようになったのが始まりだそうです。
特に、幕末の馬関(下関の雅称)は意気盛んで情熱的な志士達が派手に豪遊していたそうです。
山口県が河豚で有名になったのも、この幕末の志士達が豪快に河豚料理を楽しんだことが全国に伝えられ、それが原因として上げられるという説もあるようです。