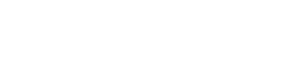2024年10月31日
 こんにちは。
こんにちは。
10月ですね。
9/2に下関で、ふぐの延縄漁が解禁になりました。
ふぐ漁が解禁されたと同時に15㎝まで育ったふぐを沖で放流するために船に積み込まれたそうです。
ふぐ漁は来年3月まで続きます。
今季の初競は、9/26に行われ、萩沖の日本海や宮城県沖の太平洋などで水揚げされた天然のとらふぐ250kgが競りにかけられました。
今年もようやく寒くなってきましたので、ふぐ鍋の美味しい時期がやってきました。
当店のふぐをお楽しみください
今回は、ふぐの毒が薬になる?という内容でお話をしようと思います。
以前にもふぐの毒についてお話ししたことがありますが、今回は違った視点からお話をしようと思います。
ひとくくりに毒を持っているのはふぐだけでなく、他にもたくさんいます。
近年、海水浴場などで見かけたり、ニュースでも時々取り上げられたりしているカツオノエボシや、子供の頃にお盆をすぎて海に入るとクラゲに刺されていつまでも痒みが続いてといったこともあります。
とはいえ、カツオノエボシはとても危険な海洋生物で、接触して刺されて死亡した例もあるそうです。
他にも、イモガイという海洋生物がいて、このイモガイはふぐ毒(テトロドトキシン)とは違う神経毒を持っています。
しかし、イモガイの毒を使って、末期癌の患者さんなどに使用されるモルヒネより強い鎮痛剤が開発されてすでに使用されているそうです。
イモガイだけでなく、ホヤや海面動物などから毒を基にして抗癌剤などが研究・開発され、現在、医療現場で使用されているそうです。
先にあげた海洋生物のように、ふぐ毒を使って麻酔薬や鎮痛剤を作れないかと研究が続いているそうです。
以前の豆知識でもお伝えした通り、ふぐ毒は神経毒で、神経の伝達口を塞いで神経伝達を麻痺させて全身の神経や筋肉を麻痺させて、死にいたってしまうという毒です。
しかし、ふぐ毒は複雑な構造をしているため、今だに解毒剤さえない状態ということのようです。
この死に至ってしまう毒を今まで、医療現場でふぐ毒で使ってこなかったのは、少量でも呼吸を停めてしまうという致命的な副作用があるため、医療では使われてこなかったことになります。
また、テトロドトキシンの解毒剤が開発されれば、医療現場でこの毒を使った麻酔薬なり、鎮痛剤を開発、使用することが可能になってくるのでしょうか?
たとえ、解毒剤が開発されたとしても、高いリスクが伴う薬品を、医療に携わる関係者が良しとすることはあるのでしょうか?
難しい選択になってくるのではないでしょうか?
テトロドトキシンは細胞を壊さない毒ということだけがわかっているだけのようなので、実用にはまだまだ遠いようです。
次回は、白子についてお話をしようと思います。