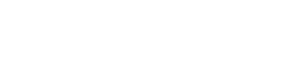2023年3月29日
 こんにちは。
こんにちは。
桜の季節になりました。
山口県の開花予想は、3月下旬のようです。
今年、一番早く桜が開花したのは、東京で3/14でした。
桜の標本木の観察を始めて一番早い開花宣言だったそうです。
山口でも桜が咲いて、お花見日和ですね。
お花見を楽しみたいですね。
さて、今回は、ふぐにまつわる俳人のことをお話ししようと思います。
俳人の「松尾芭蕉」と「小林一茶」が、それぞれふぐに対する俳句を残しています。
まず、「松尾芭蕉」は次の二つの俳句を詠んでいます。
あら何ともなきや きのふは過ぎて ふくと汁
河豚汁や 鯛もあるのに無分別
この二つの句の意味は、「ふぐは食べたは食べたけど、このまま毒にあたって死んでしまうのではないかと心配したけど、朝になって何ともなかったのでほっとした」と「ふぐは毒があるのに危険を冒して食べなくても 鯛があるのになあ」という意味になります。
松尾芭蕉は、ふぐが嫌いなことで知られていたそうです。
この句が詠まれたのは、長く続いた内乱が終わった初期の江戸時代で、豊臣秀吉によって「ふぐ食」が禁止されていた頃になります。
松尾芭蕉が食べたふぐが、江戸時代の下町の味として食べられていた「ショウサイふぐ」ではないかと言われています。
「ショウサイふぐ」は、別名があり「ナゴヤふぐ」とも呼ばれていて、とらふぐとの違いは皮にも猛毒のテトロドトキシンがあるので、ヒレも食べることはできません。
現在、「ショウサイふぐ」は筋肉と白子は食用可となっていますが、筋肉については「弱毒」とされています。
「弱毒」ですが、食べることはできます。
「ショウサイふぐ」は、釣り人ではポピュラーなふぐになります。
しかし、毒を持っていますので、もし釣れたとしても決して自分でさばくのでなく、専門の免許を持っている人に捌いてもらってから食べてください。
とはいえ、「松尾芭蕉」は、ふぐ嫌いといわれているのに、ふぐを食べたことになります。なぜ、食べたかについては本人しかわかりませんが、俳句からも食べた夜については心配で仕方なく寝ることもできないほどだったという気持ちが感じとれますね。
当時は、ふぐを食べた人が死んでしまうこともあったでしょうし、嫌いなふぐを食べなければならなかったとはいえ、「松尾芭蕉」にとっては、とても怖かったことでしょう!
次回は、「松尾芭蕉」と反対の意見を俳句にしている「小林一茶」についてお話しします。