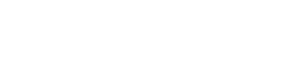2022年3月30日
こんにちは。
3月も後半になり、暖かい日が続きます。
桜も咲き、お花見日和ですね。
今回は、前回の続きで、日本大学の准教授の研究チームが、1つ目の研究で無毒ふぐと有毒ふぐの比較実験で、ふぐは卵から孵化したときから毒を持って産まれている、これを「母親からの贈り物」というお話をしました。
今回は、2つ目の研究で、「ふぐはどのように毒化していくのか」を書いていこうと思います。
2つ目の研究内容は、は「ふぐはどこから毒を体に入れているのか?」ですが、4年前に書いた豆知識で書いたように、海底のバクテリアを食べて毒を作るというのは、バクテリアが作るのは微量の毒で、ふぐが大量の毒を持つのは難しいそうです。
准教授の研究チームは、三浦半島のくさふぐを調べることにしたそうです。
くさふぐを1年半かけて調べたら、消化管からヒガンふぐの卵が発見されたそうです。
ヒガンふぐも卵巣に猛毒を持っていて、卵にも猛毒があるそうです。
ふぐは、ふぐ類同士の卵を食べて、猛毒を体内に蓄積していることがわかったそうです。
さらに、とらふぐで実験を行ったそうですが、有毒の卵を与えたところ、2日後には皮膚まで毒化してしまったそうです。
記事の文を借りれば、「食物ピラミッドの最下層にいるバクテリアが毒量が少なくても、ふぐ類を中心とする有毒の高次消費者同士で毒を循環させることで効率よく毒を獲得できる」ということだそうです。
准教授は、他にも有毒のえさを食べているのではないか考えて調べたところ、三浦半島から江ノ島海岸に生息している「オオツノヒラムシ」に着目され、3月〜4月にかけてオオツノヒラムシの産卵があり多くの幼生が海を漂い、ふぐの餌となり、ふぐ毒を形成することがわかったそうです。
7月に江ノ島海岸に行き、くさふぐを採取して遺伝子検査をおこなったところ、「オオツノヒラムシ」のDNA配列を確認されたそうです。
ふぐは地域によって毒の量が異なるそうです。
この違いは、「ツノヒラムシの資源量に依存」しているのではないかと、准教授は睨んでいるそうです。
ヨーロッパで、二枚貝によるふぐ毒の蓄積も確認されているようで、問題になっているそうです。
ふぐがどのようにして毒を持つのかが、この研究によりわかったことは良かったと思います。
同じふぐの仲間の卵を食べて毒を持ち、さらにプランクトンにより毒を蓄えているんですね。
温暖化で海水温が高くなることは、私たちが安全にたべていた魚たちが毒化されて、食が脅かされることになるんだなと思うと怖いですね。
↓ 参考にした記事
https://kenkyuryoku.com/フグの毒化に及ぼすヒラムシの影響―真のフグ毒/