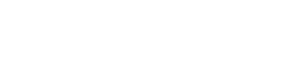2021年10月25日
 こんにちは。
こんにちは。
今年も、ふぐの季節がやってきました。
9月27日に下関の南風泊市場でふぐの初競りが行われました。
今年は、コロナ禍ということもあり、昨年より5,000円安く最高値が15,000円でした。
天然とらふぐが2.6トン、養殖ふぐが4トンで競りにかけられたそうです。
今回は、てっさ包丁についてお伝えしていこうと思います。
まず、包丁のそれぞれの名称をご存知と思いますが、お伝えします。
刃の先端から切先、切る部分を刃先または刃線、刃線が終わる角の部分が顎で切る部分を刃元といい、その他まだ名称はありますが、今回は省きます。
てっさ包丁の始まりは、大阪府堺市の水野鍛錬所が開発して大阪から広まっていったとされています。
はっきりした年代はわかりませんが、1892年頃に全国的にふぐ料理が解禁されたころにてっさ包丁が広まり始めたと言われています。
てっさ包丁は、ふぐの身欠きを薄く引くための包丁です。
特徴は、刃渡りの長さは18cm〜28cmくらいで27cmの長さが使いやすいとされています。そして、なんといっても特徴的なのは、刃の薄さです。
薄く引くには、長い刃で一気に切らないと身が崩れてしまいます。
特徴的な刃の薄さは、3mm以下の包丁もあります。
通常使われている刺身包丁や柳刃包丁よりも薄くとても狭い刃を使います。
それだけの狭さ、薄さがないと、ふぐの細胞を傷つけずに切ることは難しいです。
てっさ包丁は切れ味を重視して作られていますが、頑丈さや耐久性は他の包丁より劣ります。
その分、日々の手入れが重要になります。手入れは包丁研ぎですが、研ぐさいに刀身が長い包丁なので、曲がりやすかったりしますので、注意が必要になります。
ふぐ刺しの美味しさは、包丁の切れ味で大きく影響します。
ふぐは以前にもお話したと思いますが、低脂肪で筋肉質、弾力のある硬い身なので、厚く身を切ると食べにくいので、てっさ包丁で薄く切る必要があります。
それに、ふぐにはそれぞれに身の硬さなどに違いがあるため、最適な薄さがあります。その最適な薄さを微妙な調節ができるのがてっさ包丁なのです。
旨味が損なわれないように、適度な薄さに切るのは、職人の技術はもちろんのことてっさ包丁も必要になってきます。
ふぐの季節は始まったばかりなので、ふぐ刺しの旨味、弾力を楽しんでいただきたいので、技術とともに包丁も磨き上げますので、お楽しみください。
ちなみに、料亭のふぐ通販藤吉でもお取り寄せできますので、どうぞご利用ください。
https://www.fujiyoshi-group.com/