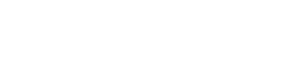2021年9月24日
 こんにちは。
こんにちは。
9月になり、暑い日がありますが、風も涼しくなり、なんとなく日が落ちるのも早くなったと感じます。
そして、ふぐ漁が始まる時期でもあります。
9/1(水)に下関市でふぐ延縄漁の第一陣が出発したというニュースをしていました。
初競りは、20日ころに行われる予定です。
一般的なとらふぐの捌き方をお伝えしようと思います。
ここで捌き方をお伝えしますが、ふぐはふぐ調理師免許の資格がないと捌けないので、一般の方は捌いたりしないでください。もし、自分でふぐを捌いて「てっさ(ふぐ刺し)」や「ちり(ふぐ鍋)」を作ってみたいと思われたら、市場などで身欠きふぐを売っていたりしますので、そちらを購入してくださいね。
ちなみに身欠きふぐとは、食べられない部分を取り除いているふぐの身のことを言います。
まず、最初にふぐは活きているものを使用するので、眉間を包丁で叩いて大人しくさせてから捌いていきます。
天然の場合は、寄生虫がついている場合があるので確かめつつ、汚れやぬめりを水で洗い落とします。
次に、背びれ、尾びれ、胸びれ、尻びれを落とします。、ひれはひれ酒にするので取っておきます。
そして、くちばし(口の部分)を切り落とし、皮を剥いでいきます。
皮を剥ぐのは、難しく技術がいりますが、慣れればスイスイと剥けます。
最初は、背中の皮→お腹と順番に剝き、あぎ(えら)と目、内臓を出して身欠き(てっさやちりにする身の部分)にしておきます。
捌き終わると、皮、ひれ、身欠き、オスであれば白子は可食(食べられる部位)、メスであれば卵巣、内蔵は不可食(食べられない部位)にそれぞれ分かれます。
一番肝心な内臓の処理をしていくときには、食べられない部分と食べられる部分はともに必ず水洗いをしていきます。
有毒部位は鍵のついた容器に入れて、専門業者さんに処理してもらいます。
捌くために使用した包丁は、しっかりと洗浄して、次にも使用していきます。
次回は、身欠きふぐをてっさ(ふぐ刺し)にする方法と皮引きの捌き方をお伝えします。
↓ ふぐ調理師免許の資格を持っておられる方がめったに水揚げされない10kg級のふぐをさばく動画がありましたのでご覧になってください。
動画は生きているふぐを捌いているので、途中エグめの画像がありますので観たくない方は再生をされないでくださいね。