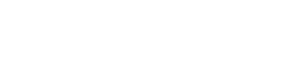2020年9月23日
 こんにちは。
こんにちは。
いよいよふぐ漁が解禁になりましたね。
今年も9月1日に、下関市の南風泊(はえどまり)市場からふぐの延縄漁船が出航しました。
資源を安定させるために、体長10cmくらいのふぐの稚魚を放流するそうです。
ふぐシーズン到来を告げる初競りは20日頃になるそうです。
今回は、ハコフグについてお話をしようと思います。
ハコフグは、フグ目ハコフグ科に属しています。
分布は、岩手県から九州の南部の浅瀬に生息しています。
稚魚のときは、岩礁海岸などの干潮時に岩などのくぼみに海水が残っていることをタイドプールといいますが、このタイドプールに、ハコフグの稚魚が残っていることもあります。
体長は20cmくらいで、特徴は文字通りで箱のように四角い体をしていて、うろこや皮膚が骨板で甲羅状になっています。体色は、黄褐色で、大きなオスは背中が鮮やかな青色になり、食は雑食性です。
ハコフグは、インド洋や太平洋などの熱帯域に9種分布していますが、このうち4種は日本産です。
ふぐといえば、ふぐ毒のテトロドトキシンで知られていますが、ハコフグは、筋肉、皮や内臓はこの毒については無毒で、各地で、食用となっています。なかでも、長崎県の五島列島などでは、「かっとっぽ」という料理があります。
ふぐ毒は問題ないですが、都道府県によっては、調理師免許がないと調理できないのでご注意ください。
ふぐ毒のテトロドトキシンは問題ないですが、違う2種類の毒を持っています。
皮膚にはパフトキシン、内臓にパリトキシンいう毒を持っています。
皮膚の毒は、ハコフグに刺激を与えると粘液性の毒を出します。内臓に関しては、毒を持っているハコフグと、持っていないハコフグがいますので、内臓は食べないほうがよさそうです。
最後に、ハコフグは皮膚と内臓に毒を持っていますが、毒に注意すれば食用、観賞用として楽しませてくれるかわいい魚です。
↓ ハコフグの泳ぎが可愛いので見てみてください。