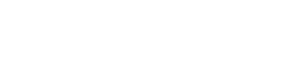2019年11月20日
 こんにちは。
こんにちは。
令和になって、初めてのふぐの季節がきました。
そして、下関で初競りが9月30日に行われ、競りはわずか30分で終了しました。
天然や養殖のふぐが競りにかけられ、1キロ25,000円で昨年より6,000円高く競り落とされました。
皆さん、とらふぐ以外にもふぐの種類は世界的に多くいることがわかっているのは、ご存知とおもいます。
もちろん食べられるふぐ、食べられないふぐ、観賞用のふぐがいます。
その中でも、「カラスふぐ」がいますが、絶滅危惧種1Aに指定されているのは、ご存知ですか?
この「カラスふぐ」は元々とらふぐと同じように高級魚として食べられていました。
とらふぐは、旨味や甘味が濃いですが、「カラスふぐ」はとらふぐに比べると身の付きがやや少ないようですが、とらふぐに劣らず美味しいふぐだったようです。
では、なぜ「カラスふぐ」と名前が付いたかというと、身体的特徴があげられます。
姿はとらふぐに似ていて、体上部と背中は黒で、腹部は白色です。とらふぐと同じに胸びれの後ろに白輪に囲まれた大黒紋があります。ここまでは、とらふぐと同じですが、「カラスふぐ」は背びれと尻びれは黒ですが、とらふぐは尻びれが白いので、この尻びれで見分けます。
体表の特徴はお伝えしましたが、体長は、50cm前後の大きさで、東シナ海・日本海西部に生息しています。
体表が黒いことから山口県では、「クロ」または「カラス」と呼ばれています。
とらふぐと同じように強毒を持っていますが、身・皮・精巣(白子)は無毒で美味しく食べることができます。
次回は、「カラスふぐ」がなぜ絶滅危惧種となったかをお伝えしていこうと思います。