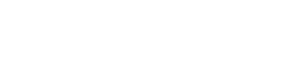2019年12月16日
 こんにちは。
こんにちは。
年の瀬も差し迫り、ますます寒くなってまいりました。
インフルエンザが流行っているようですので、体調に気をつけてお過ごしください。
前回、「カラスふぐ」の特徴をお伝えしましたが、今回はなぜ絶滅危惧種になったか」をお伝えしていきたいと思います。
なぜ、「カラスふぐ」が絶滅危惧種かというと、やはり乱獲が大きく関わっています。
とらふぐは、需要が伸びたために同様に乱獲され、数が減っていきました。
なぜ、とらふぐは、絶滅危惧種にはならなかったのか、理由としては養殖が始まったことにあります。
なぜ、養殖をはじめたかというと、生産量をカバーするために養殖が始まり、資源の保存を確保することができたためです。
でも、「カラスふぐ」は、とらふぐに次ぐ乱獲のために注意が向かないままになっていました。
気づいたときには、もう存続が危ぶまれるほどに数が減ってしまっていました。
「カラスふぐ」もとらふぐと同じように養殖で、救えれば良かったのですが、とらふぐの養殖に大きくカジをきったため、残念ながら養殖の対象にはならなかったようです。
また、中国、韓国、台湾でも漁獲されて食べられています。
1969年の「カラスふぐ」の水揚げは、3,600tありましたが、2008年には1tに減少していました。
わずか40年あまりで、99.99%まで種の生存が減少したことになります。
これは、生物が自然に増えるより、はるかに速く減少していることになり、いかに大量捕獲が原因となっているといえます。
このようなことから、2014年に『絶滅危惧1A類』に指定されました。
ですが、残念なことに、法的な縛りはありません。
このままでは、この世から「カラスふぐ」はいなくなるという警笛にしかならないのです。
もどかしい限りです。
いろいろな種類の魚、動物が、完全に絶滅してからでは、遅いのです!
今を生きる私達が、何ができるか、何をするべきかを考えていく時期に来ているのではないかと思います。