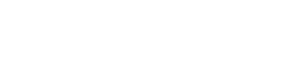2017年10月25日
 こんにちは。
こんにちは。
今回は、ふぐはどのようにして毒をもつのか・どうやって作っているかををご紹介します。
まず始めに、ふぐ毒の成分は何かといいますと、炭素・酸素・水素・窒素から出来た複雑な分子によって形成されていて、「テトロドトキシン」と名付けられています。
1960年代に日米の研究者が解明に乗り出し、京都での国際会議で発表されています。
そして、ふぐは自分で、毒を作っているのか、外部から取り入れているのかは長い間議論がなされてきました。
長く議論されてきたことが、人工養殖での結果で判明しました。
毒のない餌で育てられたふぐには毒はなかったのがわかりました。
では、なぜ毒をもつようになったのかですが、海中には小さな貝やヒトデや藻類などがたくさん生息しています。それらを食べて成長するふぐは毒を取り入れるようになったことが判明したのです。
では、自分のなかで生成された猛毒「テトロドトキシン」で、ふぐは死なないのかという疑問がおこります。
ふぐの、細胞の表面にある「ナトリウム・チャネル」というタンパク質に強く結びついます。タンパク質が、人とは違っていて、「テトロドトキシン」が結びつかないようになっています。
人が「テトロドトキシン」を間違って食べてしまうと、呼吸困難を引き起こしてしまいます。
フグ毒の謎には食物連鎖も関係しているようです。
海底を調査したところ、浅い海底からや8000メートルの海底からも、泥からフグ毒が採取されたました。
海底には、有機物を含む泥「デトリタス」食べる動物が生息していて、ふぐ毒を含む泥「デトリタス」を食べ、海底にいる動物が毒を蓄積しそれをふぐが食べてというように、食物連鎖でふぐが毒を持つようになります。
ですが、ふぐ以外の魚が「テトロドトキシン」をもっていないのはなぜかや、ふぐのみが体内に毒を蓄積できるのかや、生理的なからくりはまだまだ解明されていないことがおおくあります。