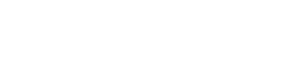2016年9月13日
 こんにちは。
こんにちは。
ふぐの毒について、ご説明します。
前回のふぐ豆知識の時に「昔よりふぐは食されていた」とお話しました。
それでは、「昔より」とはいつごろのことかと言いますと、縄文時代より食べられていたようです。
現在では、ふぐは毒を持っていて特に猛毒を有するのが卵巣や肝臓で食べられていないです。
ふぐは養殖すると、無毒のふぐになるそうです。
では、なぜふぐは毒を持つのかということですが、餌によって毒を蓄えていくとのことです。
毒を持つ経緯は、まずヒトデや貝が微生物”ピブリオ菌”を食べて体内に毒を蓄積させ、それらをふぐが食べることによってさらにふぐの体内に蓄積されて行くそうです。
ということは、ふぐは「食物連鎖」によって卵巣や肝臓に毒を有することになります。
なので、毒のある餌を食べない養殖されたふぐは、毒を持たない「無毒のふぐ」になるということです。
しかし、無毒しかいない水槽に有毒のふぐが入ると、毒化してしまうそうです。
ふぐが体内に毒を蓄積する理由としては、「外敵より身を守る効果」と「求愛」があるとされています。
ふぐが外敵より襲われそうになった時は、体内に溜めた毒を体外へ放出するそうです。
放出された毒「テトロドキシン」は、外敵にはてとても敏感で避けるため結果襲われずにすむということのようです。
雌が雄を誘うフェロモンの役割をはたしているそうです。
しかし、ふぐも毒がないと困るようで、寄生虫などがつきやすく病気になりやすくなったり、ストレスもたまりやすくふぐ同士で咬み合ったりすることがあるようです。
ふぐは自身の毒で死ぬことはあるのかというと、ナトリウムイオン・チャネルというのがあり、人間とタイプ・形が違い毒に対して耐性を備えているため、ふぐは自身の毒で死ぬことはないそうです。
↓元記事はこちらです。
http://matome.naver.jp/odai/213821