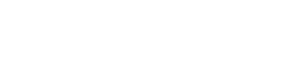2016年8月31日
 日本のふぐの歴史は、縄文時代にさかのぼり、この頃すでに食べられていたもようです。
日本のふぐの歴史は、縄文時代にさかのぼり、この頃すでに食べられていたもようです。
発掘調査では、貝塚の中からふぐの骨が発見されています。
エジプトの壁画にもふぐを食べていたような彫刻が残っているそうです。
はるか昔から食べられていたと思われます。
しかし、縄文時代などには、今のような料理方法はなく、単に焼いて食べたり、煮て食べていたらしいです。
また縄文時代では、毒のある部分に関しては、特に内蔵などは生焼けだったりするので、食べずに捨てていたんではないかと思われます。
豊臣秀吉のころにも食べられていて、朝鮮出兵の際に兵士が食べ、たくさん死んでしまったようで、「ふぐを食べることを禁ず」と禁止令を出したそうです。
また、江戸時代までふぐを食べることを禁じていたようです。
武家などは、ふぐを食べることは難しかったようですが、庶民の間ではかなり食べられていたようです。
そして、江戸時代の元禄の頃や文化文政の時代には、庶民は言うに及ばず武士階級の間でもかなり食べるようになっていったそうです。
俗にいう文化人たち(俳句、浮世絵師、落語家など)にも好んで食べられていたそうです。
ふぐを食べること解禁されたのは、明治時代に入り初代総理大臣伊藤博文公が、下関の”春帆楼”(現在もあります)に立ち寄り、海が時化ており出す魚がなかったため、仕方なくふぐ料理を出したそうです。
これを、伊藤博文公がいたく感激し、それからふぐの食文化が解禁となり、現在に至るそうです。