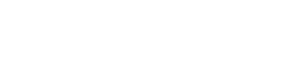2025年9月16日
 こんにちは。
こんにちは。
9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。
お盆ごろから、雨の日が少しづつ増えてきて、いまは秋雨前線が活発になっているようで、晴れた日が続かなかったりとお天気があまり良くないようです。
先月の大雨による被害があった方々にはお見舞い申し上げます。
今回は、ふぐの目についてお話ししようと思います。
以前に、ふぐは目を瞑るについてお話をしたと思いますが、今回は「目」について話していこうと思います。
ふぐはなぜ、目がとじれるかというと、瞼(まぶた)があるから閉じるというわけではないようです。
目の周りの筋肉を収縮させて目を閉じているようです。
また、とらふぐは砂に潜る習性があるため、目を保護する目的もあるようです。
目を閉じる行動は砂に潜るときだけでなく、障害物にぶつかりそうになった時や寄生虫が目に付いた時などに見られるそうです。
目を閉じる仕組みは、まず目の周りの皮膚が巾着袋の口のように中心に集まり、眼球が眼球が収まっている空間(眼窩)に引き込まれて、最後に薄い筋肉が収縮して皮膚を動かし、目を閉じることができます。
ちなみに、とらふぐの目の周りの筋肉は、毒を有している可能性があるため食べることができませんのでご注意ください。
 とらふぐ以外に目を閉じる魚はいるのかなと思い調べて見ました。
とらふぐ以外に目を閉じる魚はいるのかなと思い調べて見ました。
なんといました。
一部のサメの仲間やエイ、トビハゼの仲間です。
ふぐとは、違った方法で目を瞑っているようです。
一部のサメは、獲物を捕食した時に暴れる獲物から目を守るために「瞬膜(しゅんまく)」という眼球表面を覆う膜を使っています。
軟骨魚類といわれる全身の骨が全て軟骨でできたサメやエイのことなんですが、これらの軟骨魚類の一部は「瞬皺(しゅんしわ)」と呼ばれまぶたの代わりに目の下の筋肉を上げて目を覆うものなどがいるそうです。
勝手な思い込みで、魚は目を閉じないものと思っていました。
ですが、ふぐだけでなく目を閉じる魚は数種類いて、それぞれの魚の方法で目を守ることをしているんですね。
次回は、ふぐの尾鰭についてお話ししようと思います。