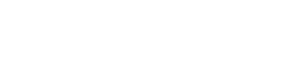2021年4月14日
 こんにちは。
こんにちは。
4月になり、桜も散り、少しづつ新緑も芽生えはじめましたね。
毎年4月29日に下関でおこなわれていた「ふくの供養祭」ですが、昨年もコロナの影響により中止になりましたが今年も昨年同様にコロナのため中止となったようです。
今回は、ふぐの仲間「マンボウ」についてお伝えします。
マンボウは、フグ目マンボウ科マンボウ属に分類されています。
日本近海では「マンボウ」と「ウシマンボウ」がおおく見られるそうです。
とらふぐなどは、体を風船のようにふくらませることができますが、マンボウは体をふくらませることはできません。
ふぐの仲間では一番大きく、成長すると全長約3mになるそうです。
形態は、ユニークな体型をしていて、右上の絵のようになっていて、背びれと尻びれがあり、とらふぐは尾びれがありますが、マンボウは尾びれがなく、舵びれとなっています。
この舵びれは、背びれ・尻びれの一部が変化してできた特殊な舵びれで、泳ぐときに方向転換をするときに使います。
とらふぐなどと一緒で、マンボウも腹ビレはありません。
目にはまぶたはないのですが、ふぐのなかまであるマンボウは目の周りの筋肉を使って閉じることができます。
歯は、ふぐの仲間になるので板状の歯が上下に1枚ずつあり嘴(くちばし)のようになっています。
泳ぐときは、背びれと尻びれを大きく左右同時に動かすことで泳ぐことができます。
皮膚は、厚く粘膜で覆われていますが、表面には寄生虫が付着しているそうです。
目にも寄生虫がついていて、マンボウの目はほとんど見えていないそうです。
そのため水族館で飼育されているマンボウは、水槽の壁にぶつかってしまうこともあるそうで、けがを予防するために透明なフィルムを貼って、マンボウを守っているそうです。
ほかにも特徴があるようなので、次回にお伝えしようと思います。