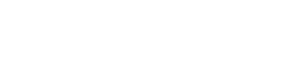2018年12月18日
 こんにちは。
こんにちは。
すっかり寒くなり、ふぐが美味しい季節になりました。
また、3ヶ月前のことになりますが、ふぐ漁が解禁され、初競りがありました。
今年は、最高値が1キロあたり19,000円だったようです。昨年と同様の競り値がついたようですね。
さて、今回は、ふぐはなぜ高級魚になったのかをご紹介していきますね。
ふぐ料理を食べるお店も限られていますし、食べに行けばすごく高いです。肝臓や卵巣以外は余すこなく食べることができるので魅力です。
食べ方もいろいろありますし、とらふぐだけでなく真ふぐもたべると美味しいですよね (^^)
この食べ方(料理)には、一匹の魚で、煮こごりや刺身、から揚げ、天ぷら、ちり鍋、最後にふぐ雑炊とフルコースができます。これらの食べ方(料理)がふぐの話題性の高さが価格を刺激して高くしているのかもしれないですね。
2年くらい前に“ふぐの歴史”について豆知識で書いたと思いますが、ふぐは明治維新を境に食べられるようになったと書かれていました。
以前読んだ本に、“高度経済成長を迎えて、日本人の消費行動が変化した”とありました。
食への行動が“美食志向”に変わったことにあるとも書かれていました。
高度経済成長期に、美食志高の高まりとともに、美食家の北大路魯山人や三島由紀夫といった文化人がふぐを取り上げました。そして、そのことでとらふぐの評価はさらに上がり、高級ブランドとしてのイメージを高めていったといえるかもしれない、とも書かれていました。
また、エルメスやヴィトンなどと同じように一般庶民がなかなか持つことができないと同じように、なかなか食べることのできない何万円もするとらふぐを食べて優越感を味わったりすることで、他者との差別化を図ったことにあるとも書かれていました。
さらに、ふぐは彼岸から彼岸までと言われ季節が限られていたり、皇室への献上などというように話題性もあることから、ブランドとしての価値を備えていったといえるかもしれませんね。
日本人の食行動の変化と文化人により作られたイメージもあり、また日本人として食性の適合によって天然とらふぐのブランド化・高級化が形づくられました。
以上のことから、食のグルメ化・贅沢化が背景にあり、とらふぐはこのグルメ化・贅沢化を象徴している魚といえます。