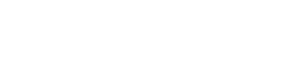2017年3月13日
 こんにちは。
こんにちは。
今回は、季節によってふぐの毒の強さがかわることについてお話します。
昔よりふぐの旬は、秋の彼岸から春の彼岸までと言われています。
特に、4月のふぐは危険というのはご存知でしたか?
「なたねふぐ」という言葉がありますが、これはふぐの種類ではなく菜種の花が咲く頃のふぐという意味です。春を表す季語で、歳時記にも載っています。
ふぐの、テトロドキシンは季節によって強さが異なり、秋口は弱くそして春先は強くなると言われています。ふぐ毒の特性についての研究が昭和15年頃に行われ、科学的にも立証されています。
特に春の彼岸を過ぎたふぐは、身に締まりがなく水っぽいため、旬のころに食べる味とは違います。
なお、この春の彼岸の時期に呼ばれるふぐがいて、「ひがんふぐ」と呼ばれています。
「ひがんふぐ」の特徴は、体全体に粒状の突起があり、体長は30cm 程度の大きさになります。
そして、別名「なごやふぐ」とも呼ばれています。
なぜ、「なごやふぐ」と呼ばれているかというと、「あたったら身のおわりである」というダジャレから由来されついたと言われています。
ではなぜ、「ひがんふぐ」なのかですが、春の彼岸の頃に産卵をするためにこの名前があると言われていますが、春に産卵するのは、このふぐばかりではなく「とらふぐ」や「まふぐ」も早春から初夏にかけてが産卵期にあたります。
なぜこの「ひがんふぐ」に「彼岸」の二文字がつけれたかというと、「春の彼岸によく捕れる」や「食べると彼岸に逝ってしまう」という説もあります。
この「ひがんふぐ」には、皮に毒があり、また毒性も強く、先に述べた説にあるように「食べると彼岸に逝ってしまう」という意味からもわかるように、あたる=あの世とかけてこの名前が付いたと言われています。
ですが、この「ひがんふぐ」は食べると違い、身は硬くしまっていて美味しいですよ(^^)。